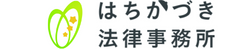「自分が他界した後、遺産をどう分けるか決めておきたい」という方は多いです。
そのためには、「遺言(遺言書)」という制度を活用します。
ただ、法律上有効な遺言と認められるためには、きちんと要件を満たす必要があります。
要件を満たさない遺言や、要件を満たすかどうか問題になる遺言だと、せっかく書いたのに意味が無かったり、それが原因で相続人間でトラブルになるリスクもあります。
そのため、遺言を作りたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
ここでは概要を解説しますが、悩まれたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
①自筆証書遺言について
自筆証書遺言(法律用語で「いごん」といいます)について
遺言とは、生前にご自分の財産を死後誰にあげたいかを決めることです。
「自筆証書遺言」であれば、紙・ペン・ハンコさえあれば作ることができます。
自筆証書遺言のメリットとしては、
①作るだけであればほとんど費用がかからないこと
②作るために証人が不要であること
があります。
もっとも、遺言には有効に成立するための要件があり、ご自分の考えていることを綴るだけでは有効な遺言にならないことを注意する必要があります。
要件については民法に書かれています。
決まった要件を満たしていない遺言(のようなもの)は無効であり、全く意味のない落書きになってしまうので、ご注意ください。
民法で定められた自筆証書遺言の要件は以下のとおりです。
- 全文を自筆すること
- 正確な日付を自筆すること
- 署名すること
- 捺印すること(以上、民法968条1項)
<例えばこんな自筆証書遺言は全て無効になります>
- パソコンで作成した遺言
- 口で伝えた内容を第三者が書き起こした、自筆でない遺言
- 捺印がない遺言
- 平成●年●月吉日など、日付が特定されていない遺言
- 文字ではなく、絵や記号で表現した遺言
- 暗号形式の遺言
- ビデオで撮影した遺言
など、法的に無効になる遺言はいくらでも考えることができます。
せっかく遺言を書いたのに、無効になるとその内容は民法上、全く反映されない事になってしまいます。
ですので、自筆証書遺言を作成する場合でも、専門家により、法的に有効な遺言かどうか、という点をチェックしてもらうことはとても重要です。
検認という手続
自筆証書遺言を作成する場合、もう一つ重要な点があります。それは、遺言者が亡くなった後に、誰かが必ず検認という手続を採る必要がある(民法1004条)という事です。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所へ持っていき、このような遺言書が残されていたという事実を裁判所で確認してもらう手続をいいます。
検認をすることにより、検認時点の遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することができます。
検認手続をする人は、遺言書を生前から保管していた方や遺言書を発見した相続人の方です。
それらの方が家庭裁判所に対し検認手続の申立てを行うと、被相続人の方全員に「●月●日に検認を行うので家庭裁判所に来てください」、という内容の通知が届きます。
もし遺言書に封がされている場合は検認の日に開けることになるので、それまで中身はわかりません。
遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認手続を行わないと、せっかく遺言書が残されていても執行できなくなってしまうので注意が必要です。
遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認なしに遺言を執行したり、封がされている遺言を家庭裁判所の外で開けてしまったりした場合は、五万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
この場合、遺言自体は無効にならないのですが過料という罰を受けることになります。
そして、遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した人は、相続欠格者となり、相続人の地位を失ってしまいます(民法891)。
検認については裁判所のホームページが参考になります。
検認の申し立てを行うときには、申立書を記入し、戸籍等様々な書類を集める必要があります。
もし、手続きをする際にわからないことがあれば、専門家に依頼することでストレスなく検認手続を進めることができます。
証拠確保の重要性
この点は民法上求められているわけではありませんが、大切なことですのであえて記載しておきます。
自筆証書遺言は第三者から見ると、本当に本人が書いたものなのかどうか全く判断できません。
ですので、相続人間で争いが起こる可能性があります。
その可能性を少しでも減らし、問題のない相続を行うために、民法で定められている要件を満たすだけではなく、出来るだけ証拠を残しておくことをお勧めいたします。すなわち、
「この遺言は遺言作成者が、自分の意思で書いた」
ということを証明するための手段を用意しておくわけです。
<例えば証拠作成の方法としてはこのようなものがあります>
- 遺言作成途中の写真・ビデオなどを撮る
- 作成が終わった遺言書を本人が手に持ち、内容が見えるようにした上で写真やビデオを撮る
- 捺印を実印で行い、印鑑証明書と一緒に保管する
- 信頼できる人や専門家に写しを預けておく
- 専門家に立ち会ってもらう
このような証拠を確保しておけば、後の争いの可能性をかなり減らすことができます。
さらに争う余地を減らすため、遺言の財産目録を作成する必要がある場合もあります。財産目録は、特に形式はありませんが、財産を特定するための添付書類として不動産の登記簿謄本を取得するなど、気を付けるべきことは多数ありますね。こちらの点についても、専門家に必要書類などを聞くことが有効です。
=自筆証書遺言の記載例=
遺言書
遺言者は遺言者の有する一切の財産を妻■■(昭和●年●月●日)に相続させる。
平成●●年●●月●●日
遺言者 ●● 印
可能な限りシンプルにすればこのような形式になります。
もちろん、財産を分割して遺したい場合は、もう少し複雑な形式になります。
複雑な形式であれば、それだけ、誰が読んでも同じ意味になる文章として残す事は難しく、争いになる可能性が高くなります。
複雑な遺言を作成しようと思うときは、専門家に一言お声かけください。